人とペットが幸せに暮らすためのライフスタイルを提案する機関誌『愛玩動物 with PETs』。
ペットにかかわるさまざまな情報や協会からのお知らせ、連携団体の活動の様子を掲載しています。
協会会員の方には、定期的に機関誌をお届けいたします。協会会員についての詳細はこちらをご覧ください。
機関誌のバックナンバーなどの購入は、こちらからお申し込みください
307号(2026年1月号)

馬を知る
[Introduction]
愛玩動物としての馬の魅力 ~〝心の馬温泉〟の効用~
[第1章]「ウマ」という生きもの
❶ ウマの起源
❷ ウマの生物学的特徴
❸ ウマの品種と毛色
Column 日本の在来馬
[第2章]馬の文化史
❶ 馬との関わりの世界史
❷ 馬との関わりの日本史
❸ 現在の馬事情
❹ 日本に伝わる馬文化
フォトエッセイ 牧場の厩舎猫たち
海外レポート すべての動物に優しい馬大国・スウェーデン
[第3章]現代日本で働く馬たち
1 乗用馬
馬と一体になって挑む「馬術」は動物と一緒に行う唯一のオリンピック競技
2 セラピーホース
療育(児童発達支援)の現場でセカンドキャリアを送る引退競走馬
3 神馬
子どもの情操教育や地域活性化にも貢献する御神馬さま ほか
306号(2025年11月号)

公益社団法人日本愛玩動物協会の歴史と公益事業
[第1章]日本愛玩動物協会の歴史と主な事業
1)日本愛玩動物協会設立の経緯
2)適正飼養の普及啓発活動の意義
・日本愛玩動物協会の主な出来事(表)
3)動物愛護・適正飼養の普及のための活動
1動物愛護·適正飼養教育
①愛玩動物飼養管理士養成事業
②ペットオーナー検定
③ペット共生住宅の適正化推進プロジェクト
④愛犬(愛猫)飼育スペシャリスト検定
⑤教育動画シリーズ「学びの部屋」
⑥機関誌『愛玩動物 with PETs』
⑦各種書籍の発行
⑧適正飼養パンフレット
2ボランティア活動と活動支援
3セミナー・シンポジウム
4調査研究・調査研究助成
5国や自治体への協力支援活動
6動物専門学校への学生教育支援活動
・愛玩動物飼養管理士教育・認定事業の総合的な体系(図)
・公益社団法人日本愛玩動物協会の事業概要(表)
4)日本愛玩動物協会の今後の取り組み
[第2章]動物愛護· 適正飼養の昔と今
・ペットの飼い方·暮らし方
犬のいる暮らし 猫のいる暮らし ペットの高齢化 高齢者とペット
子どもとペット エキゾチックペット ペットと暮らす住まい
ペットツーリズム ペットの災害対策 ペットとIT
・ペットを取り巻く産業
生体 ペットフード 獣医療 その他のサービス
・行政機関の動物愛護管理施策
行政施策の変化 動物愛護管理施策の役割の多様化 ほか
305号(2025年9月号)

災害時における「人とペットの救援活動」
[第1章]主な自然災害と被災ペットの救援活動
①災害時のペット救援活動の歴史と課題
②40年で進んだ法整備
③令和6年能登半島地震におけるペット救援活動
事例紹介)国・自治体・民間団体の協働例
トレーラーハウスを利用した被災ペットの一時預かり施設
Interview)山口千津子先生(公益社団法人日本動物福祉協会顧問)
社会や飼い主の意識が変わった今、求められる“協働のための仕組みづくり”
年表)これまでの主な自然災害とペット救援活動
[第2章]被災ペットのためのボランティア活動
①災飼い主を支えるペットのボランティア
②ペットのボランティアの種類
③被災地でのボランティアの心構え
④現地に行かなくてもできること
⑤災害が起こる前からできること
[第3章]「避難所」と「シェルター」の種類と注意点
①「避難所」と「シェルター」の違い
②避難所における被災ペットの収容方法
③シェルターの種類と収容方法
④シェルターメディスン ほか
304号(2025年7月号)

ペットの社会化
[第1章]ペットの社会化の必要性
インタビュー)獣医行動診療科認定医に聞く
犬や猫の問題行動の治療はカスタムメイドで行うことが基本
[第2章]犬の社会化のためのしつけの実際
①社会化期に行うしつけの基本
②飼い主が行う「社会化トレーニング」
1基本のしつけ
・体をさわられる ・豆知識)正しい抱っことは
・クレートやキャリーケースに慣れる ・豆知識)抱っこ散歩の効果
・首輪を着ける ・リードを着ける ・ハーネスを着ける
・お手入れをする ・洋服を着せる
・生活音に慣れる ・体を濡らす ・ほかの人に慣れる ・車に乗る
2社会化期以降のしつけ
・留守番 ・豆知識)すでに苦手な物がある場合
・コミュニケーション ・トイレトレーニング ・豆知識)散歩で出会う物事
[第3章]専門家と一緒に行う「社会化プログラム」
犬編)犬の専門家から学ぶ知識とテクニック
事例① 動物病院で行われる子犬の社会化プログラム
事例② 自治体主催の社会化・しつけ方プログラム
猫編)猫の専門家から学ぶ知識とテクニック
事例③ 動物病院で行われる子猫の社会化プログラム ほか
303号(2025年5月号)

日本人とペットとの共生文化のカタチ
[part.1]ペットとの暮らしの風景
1)日本人と動物との共生の歴史と背景
2)動物への畏敬と感謝の気持ち
特別インタビュー)林 良博先生(国立科学博物館顧問)
3)現代におけるペットライフの多様性
①データで見る「ペットとの暮らし」
Column 1)多様に広がるペット業界
Column 2)需要が高まるペット関連サービス
②ペットとの生活スタイル/③ペットのトレンド/④情報・メディア
Column 3)「MADE IN JAPAN」なペットたち
[part.2]ペットの医食住学遊
1)ペットの医療と健康
Column 4)人とペットの共生のための「マイクロチップ情報登録制度」の効用
特別寄稿)藏内勇夫氏(公益社団法人日本獣医師会会長)
2)ペットの食生活
3)ペットとの住まいと暮らし
①ペットと共生する住まい
Column 5)ペットとの暮らしをより快適にするためのヒント
②ペット用品/③ペットがいる暮らし
⑴子どもとペット/⑵高齢者とペット/⑶ペットの災害対策
4)学び
5)遊び(余暇・レクリエーション)
①ぺットツーリズム/②ペットアクティビティ/③お出かけ時のマナー
[part.3]共生を支える社会の形成に向けて
1)ペット関連法制度の現状
Column 6)環境問題解決への取り組みから学ぶ 人と社会の意識改革
2)人間を取り巻く動物との関わり
3)ペットとの共生を支える取り組み事例
Column 7)人とペットが共生する豊かな社会の実現に向けて ほか
302号(2025年3月号)
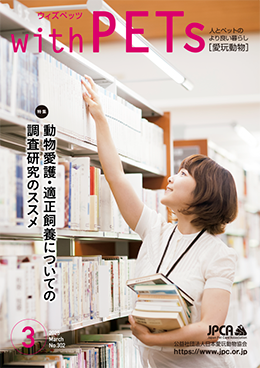
動物愛護・適正飼養についての調査研究のススメ
[Introduction]
世の中を変えるために必要なのは調査研究による“科学的根拠” と“知的好奇心”
[第1章]大学などの教育・研究機関
① 大学とは
Interview 大学研究者に聞く動物行動学の調査研究
② 本協会「家庭動物の適正飼養管理に関する調査研究助成」の概要
[第2章]調査研究のための「学会」活用法
① 学会とは
② 動物関連の主な学会・研究会
事例紹介 人と動物の関係性のトレンドがわかる「ヒトと動物の関係学会」
学会活動エッセイ
世界を大きく広げてくれた「ヒトと動物の関係学会」との出会い
[第3章]公益団体や民間企業などが行う調査研究
① 公益や社会貢献のための調査研究
② 公益法人や一般法人などの団体
③ 民間企業など ほか


